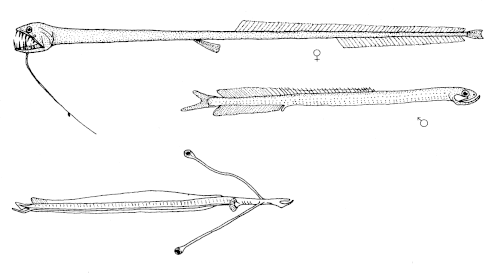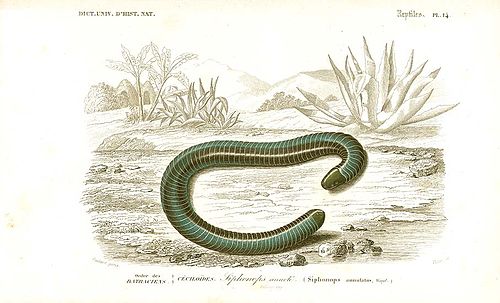写真出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/アミガサハゴロモ
なんだか今年はたくさんの
小さな蛾に似た生き物が
外灯や網戸やバルコニーにいる・・・
と思い、ちょっと調べましたのが
今回ご紹介する、
「チュウゴクアミガサハゴロモ」です。
1.5センチほどと、小さなこの生き物は
蛾に似ていますがカメムシの仲間だそうです。
なるほど、そういえば
カメムシをたくさん見かける時期と
重なっているような・・・。
日本では2018年ごろから
みられるようになった、
外来種だそうです。
綿のような卵を木に産み付け、
幼虫や成虫が集団で樹液を吸うことで
樹木を痛めるとのことです。
県ごとに害虫として
注意喚起しているようですので
気になる方は一度ご確認ください。